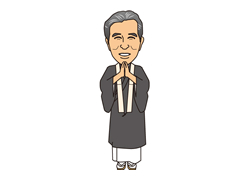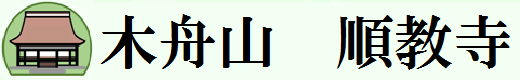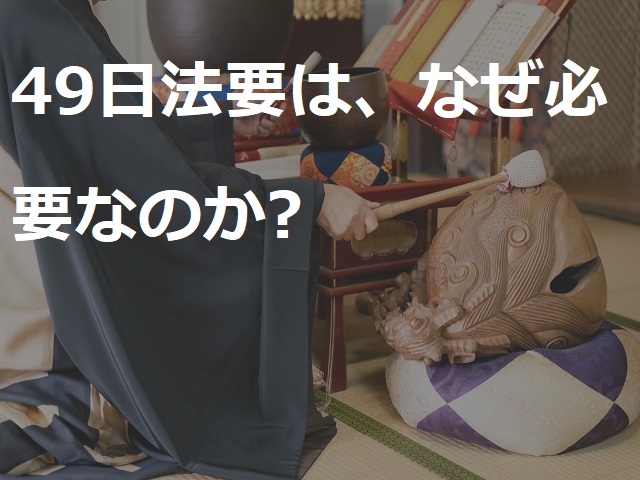現在、祖父の49日法要を行おうと考えています。家族でいつ頃行おうかと考えていた際に、弟から49日法要をそもそもする必要があるのかと質問をされ上手く回答する事ができませんでした。49日は、そもそもやる事が当たり前だと思っていたので、弟が思っているような疑問はありませんでした。弟に聞かれて初めて、49日を行わなければいけない明確な理由を答える事ができない自分に気づきました。お恥ずかしい限りですが、49日を行わなければいけない理由について改めて教えていただけないでしょうか。(門徒T.Aさん)

う~ん。この質問の答えて簡単そうに見えて難しいですよね。一番定番な答えは、丁寧な供養のためと思うんですけど、それだけだと不十分なような気がします。
そうだね・・。最近は、この質問を受ける事が多くなってきたよ。それじゃ~今日は49日法要の考え方について説明しよう。
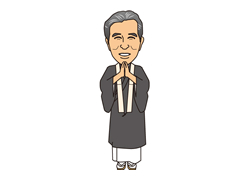
目次
49日法要の意味とその歴史
仏教において四十九日という期間は、人が亡くなってから次に生まれ変わるまでの間の期間のことを意味しています。

この49日の期間を中陰(ちゅういん)や中有(ちゅうう)とも言います。
この中陰の期間内に、7日ごとに故人のために供養を行えば、亡くなられた方が良い所へ生まれるとされています。49日法要も中陰の期間の間に行う法要の1つです。
日本に伝わっている仏教は、中国で道教の影響を多分に受けています。道教の教えには、7日ごとに閻魔様などの冥界の十王に生前の行いを裁かれるという十王信仰の考え方があります。

この十王信仰の考え方が日本に伝えられている仏教にも加えられています。十王とは、地獄において亡者の審判を行う10尊の裁判官のことをさします(詳細は下記表を参照してください。)。
それぞれの裁判官には定められた審判の日があり、それぞれの裁判官は各審判日において死者の生前の行いを裁くとされています。
その後、日本に伝わった仏教は十王をそれぞれ十仏と相対させるようになりりました(詳細は下記表を参照してください。)。
| 審判日(審理) | 十王一覧 | 日本での呼び名 |
|---|---|---|
| 初七日 | 秦広王(しんこうおう) | 不動明王(ふどうみょうおう) |
| 二七日 | 初江王(しょこうおう) | 釈迦如来(しゃかにょらい) |
| 三七日 | 宋帝王(そうていおう) | 文殊菩薩(もんじゅぼさつ) |
| 四七日 | 五官王(ごかんおう) | 普賢菩薩(ふげんぼさつ) |
| 五七日 | 閻魔王(えんまおう) | 地蔵菩薩(じぞうぼさつ) |
| 六七日 | 変成王(へんじょうおう) | 弥勒菩薩(みろくぼさつ) |
| 七七日(四十九日) | 泰山王(たいざんおう) | 薬師如来(やくしにょらい) |
| 百箇日 | 平等王(びょうどうおう) | 観音菩薩(かんのんぼさつ) |
| 1周忌 | 都市王(としおう) | 勢至菩薩(せいしぼさつ) |
| 三回忌 | 五道転輪王(ごどうてんりんおう) | 阿弥陀如来(あみだにょらい) |
通常は、7回の審理で、死者の生まれ変わる場所が定まるとされています。生まれ変わる場所は、六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道)のうちのいずれかの場所だとされています。

7回の審理ののちに、地獄道・餓鬼道・畜生道と呼ばれる三悪道に落とされた場合の救済措置として追加で3回の審理(百箇日・1周忌・三回忌)があるとされています。
そして、初七日法要などの葬式以後の法要が49日までの間に7回あるのは、審理のたびに十王に対し死者への減罪の嘆願を行うためだとされています。
死者の裁きは、死者の生前の行いとこの世に残された遺族の追善供養の態度で決定されるとされています。

そして、百箇日、1周忌や三回忌などの法要は追加の審理の三回のために行う法要あり、法要を行う目的も死者の減罪の嘆願のためです。
以上が、日本仏教における基本的な49日の考え方と49日法要を行わなければならない理由です。
浄土真宗における49日法要の考え方
「49日法要の意味と歴史」の項で触れた一般的な49日とは異なる考え方を基に、浄土真宗では49日法要を実施しています。
浄土真宗は、阿弥陀仏さまの本願を信じ念仏するものは、この世の命を終えると、浄土に往生して速やかにさとりを開くという教えです。

そのため、初七日からなる法要は追善供養という意味合いでは行いません。
代わりに、浄土真宗の教えに触れ、故人を偲びそしてご自身の人生がさらに豊かになる道を模索していただく場だと考えられています。
49日法要の必要性
49日法要の必要性は、宗派や人により違います。
一般的な仏教では49日法要は、故人が死後の世界でも心安らかに暮らすことができるために必要だと考えています。
浄土真宗においては、浄土真宗のみ教えにふれ自身の人生が豊かになる道を模索していただくために必要だと考えています。

葬儀や49日法要などの場は、生と死が交わる瞬間です。
葬儀や49日法要などの場を除いて、生きる者が普段の生活の中で死を意識することはほとんどありません。
死は我々にとって非常に身近な事象ですが、我々は普段その身近な事象についてほとんど考えないのではないでしょうか。
葬儀や49日法要などの場は、そんな我々に対して死という事象を再認識させてくれる貴重な場であるわけです。
死について考える事は、生について考える機会にもなります。自分の死・家族の死などについて考える事で、生きている時間というのが束の間であり、尊いということを再認識することができます。
そして、再認識することで自分のこれまでの生き方についてもより深く振り返ることが可能となると思います。
葬儀や49日などの法要の場は、故人を偲ぶ場であるとともに自分の生き方についても考える事ができる貴重な場でもある訳です。
そして、その貴重な場において仏教という人生の苦悩について悩み尽くされた教えを聞くことで、自分の人生がさらに豊かになる道を模索していただくことが可能となると思います。
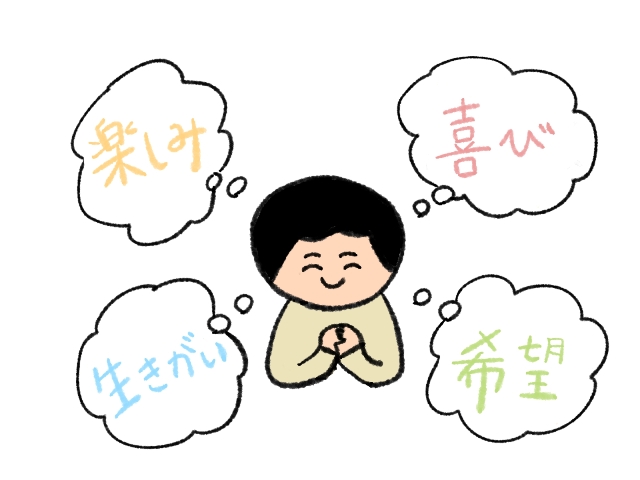
以上の事から、49日法要は必要だと考えます。

なるほど、49日法要を行う背景にはそういう理由があったんですね。私も、これまでは供養をする事が一番の理由だと思っていましたけど、今後は自分の人生の振り返りも真剣にしようと思います。
49日などの法要の場はお経をあげて難しい説法を聞く場だととらえている人が多いけど、人生について考えてもらう場でもあるんだよ。だから、今後はぜひお参りだけでなく自分の人生の振り返りをしてもらえればと思うよ。