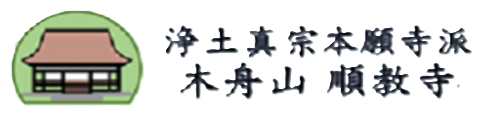当寺院の系譜
順教寺は、1574年(天正2年)頃、教春により開基されました。以来、様々な時代の移り変わりを乗り越え、脈々と受け継がれて現在に至ります。
歴代住職
| 開基 1574年 (天正2年) | 第一世 教春 (きょうしゅん) | 1780年 (安永9年) | 第八世 頓乗 (とんじょう) |
| 1602年 | 第二世 正順 (しょうじゅん) | 1804年 (文化元年) | 第九世 速満 (そくまん) |
| 1669年 (寛文5年) | 第三世 空玄 (くうげん) | 1824年 (文政7年) | 第十世 楽聴 (らくちょう) |
| 1703年 (元禄16年) | 第四世 残立 (ざんりゅう) | 1873年 (明治6年) | 第十一世 正覚 (しょうかく) |
| 1735年 (享保20年) | 第五世 立海 (りゅうかい) | 1924年 (大正13年) | 第十二世 正俊 (しょうしゅん) |
| 1747年 (延享4年) | 第六世 亮淳 (りょじゅん) | 1972年 (昭和47年) | 第十三世 良信 (りょうしん) |
| 1773年 (安永2年) | 第七世 立好 (りゅうこ) | 1977年 (昭和52年) | 第十四世 文雄 (ぶんゆう) |
当時院の歴史
順教寺は、教春(きょうしゅん)により1574年(天正2年)に開基されました。その後、当寺院第二世の正順(しょうじゅん)の代に1663年(寛文3年)に現在の位置に移ったとされています。
当寺院が現在の位置に移る前は、毛利家の家臣であった吉川経好(後の市川経好または市川常吉とも呼ぶ)の土居屋敷(中世豪族の屋敷の呼び名。その屋敷を中心として集落があった。)があったとのことです。その市川経好の館であった名残が順教寺の石垣として現在も残っています。

市川経好の武家屋敷のものとされる石垣

当寺院の山門前の石垣の全体像
市川経好は、1557年(弘治3年)に毛利元就に行政手腕が認められて山口奉行に任じられて、高巌城(現:山口県)に入り高周防国山口を治める事になったそうです。市川経好が山口に去り、当寺院が現在の位置に移ったとされる1663年までにどのようにこの武家屋敷が管理されていたか詳細は現段階では分かりません。ただし、毛利家の管理下にあった事が推察されます。
理由は、毛利輝元が関ヶ原の戦いで敗れ、安芸(現:広島)から周防・長門(現:山口)へ移る際に毛利家よりこの土地を寄進されたという記述が高田郡村々覚書に残っているからです。そういった経緯で、1663年の正順の代に現在の位置に順教寺が建立されたとのことです。

高田郡史(資料編)p38より抜粋しています。
余談ですが、市川経好には市川局という妻がいました。その市川局は、永禄12年(1569年)に大友宗麟の支援を受けた大内輝弘が市川経好の居城の高巌城を包囲しました。大内輝弘が高巌城を包囲した際、市川経好は不在であり、城には妻の市川局と僅かな家臣、守備兵しか残っていませんでした。しかし、市川局は城兵を指揮して大内軍を撃退し、城を守りきりました。この活躍により、後に毛利輝元から市川局は感状を受けています。その感状は現在も残っています。
教春が現在の地に順教寺を建立して以降、14世の文雄までの間に本堂を拡張したり庫裏や客殿の建設を行い、現在の順教寺の姿となっています。
当寺院の歴史的遺物
鐘楼の梵鐘

御鋳物御筆頭の植木直正作とされています。
喚鐘

鋳物師可部住細田氏と記載されています。